
入浴介助で虐待を疑われる痕跡を
見つけた場合の対応について教えて下さい

まずいつからその傷なり内出血が出来たかですよね。
数日の間にヒヤリハットとして挙がっていたかにもよりますね。
あと受傷の程度ですね、これは施設によって対応や
定義が別れる所でしょう。
内出血は全て事故として処理するのか
微少な剥離はヒヤリハットにするのか等。
明らかに骨折が疑われる腫脹、内出血や
その人のADLで説明の付かない部位にある受傷等は
施設長、看護師長と事務局長と発生元の主任、副主任
相談員によるヒヤリングと行政に対する報告
家人に対する説明をうちの施設では行います。

利用者さんによりますが
認知能力に問題のない方であれば本人に聞きます。
認知能力に障害のある方ならば1番上に報告します

まずは相談でもいいと思いますよ😊
虐待かまずは話合うのも必要だと思います。

まずは虐待があるかどうか
あらゆる手法で確認していきます。
そして結果の有無に関わらず
ご家族様、場合によっては行政へも報告です。

日頃のリスクマネジメントも重要ですよ

個人というより施設として
事業所として法人としての対応が問われると思います。

SNSでもご意見頂きました。

施設系の場合は
上司に報告→ケアマネ→看護師→包括
訪問介護→ケアマネ→包括ですね。
私はサービス提供責任者なので
緊急性が有れば、直包括も有ります。

上司に報告し、上司と共に痕跡の状況が分かる
専門職(看護師・医師)とその痕跡を確認します
そこからは、上司と専門職の判断によって分かれると思いますが、
【虐待の可能性が高い】との判断となった場合は、
地域包括支援センターに報告・相談の上、
包括と足並みをそろえての対応となるでしょうね

実は今いる施設でそういう疑いがありました。
犯人捜しをするのではなく、みんなが打撲痕とか、
怪我の状況に敏感になる事が大切です。
包括にいうのも大切ですが、
外部に漏れると事案が大事になるので、
事象が小さいうちに解決を図る事が大切だと思います。

まず、その傷の形状を確認します。
故意的な跡なのか、偶然的な跡なのか。
そして、気付いてたスタッフがどれだけ居たのかを確認。
同時に受診や治療が必要なのかの判断を医療職に確認。
直ちにカンファレンスを開催し、介護過程をフィードバック。
跡が残るのには様々な理由があるはず。
犯人探しではなく、なぜこうなったのか?を見つけ出す。
それが【故意的】な場合は、指導に入る。
【故意的】【偶然的】どちらであっても
関係者には謝罪をし、これからの対応手順をお伝えし了承を得ます。
また、対応手順を実施した際には報告を行ない、改善策を提案していきます。

居宅ケアマネです。
少し趣旨と違うと思いますが、
こんなこともあることをお伝えします。
ショート利用後にあざ形成をご家族が
発見し苦情になったことがあります。
ショート送迎担当者が原因を調べて
家族に返事するのを怠り、
翌日ご家族から担当ケアマネであるわたしに
連絡があり今後はショート利用しないと宣言されました。
内服の関係であざになりやすく、
いつまであざが無かったかも
わたしが調べて判明したのですが、
ご家族は虐待を疑われたまま、
ショート利用は終了しました。
また、ショートスタッフのあざに対する認識と、
ご家族の認識にズレがあることで
生じた危機感の違いが苦情に発展した原因だと思います。

ホウレンソウは自分を守るために
絶対必要ですよねー

本当にそうです。
そこを怠っては、後からいくら説明してもね、、

そうそう そこです。
自分だと記録バタバタで曖昧になるけど
ケアマネが記録してくれたり相手が記録してくれたりするので
記録しておいて下さいと付け加えて報告してます。
行政にも場合によっては 事故報告必要かも聞きますよ。
自分を守ると介護福祉士を守るためです。
会社は何もしてくれない& 行政に報告はしないが通常。
都合が悪いから・・・

まずは報告。
対象者の安全などを確保した上で
その後検証と追及がマニュアルになるようです。
隠ぺいしようとせず、真摯に現場を保存することが
次のリスクマネジメントに役立つと信じています。

その他、ご意見随時お待ちしています!


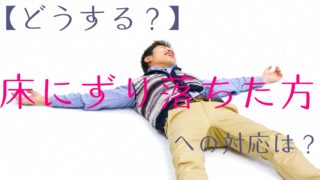
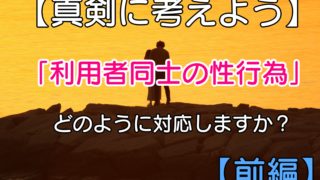
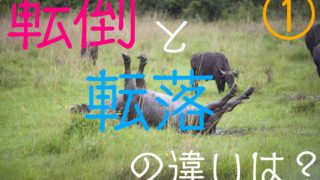
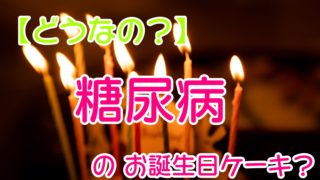

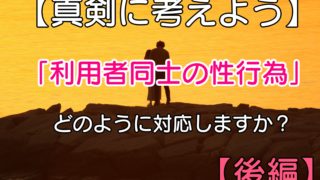

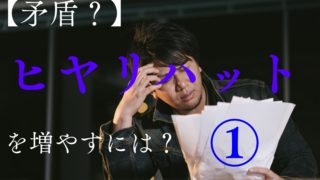

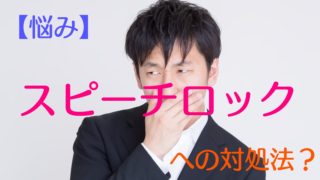
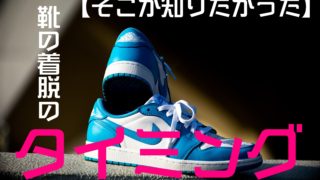
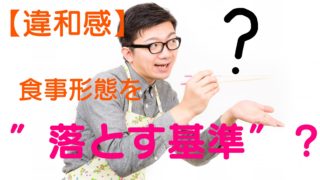
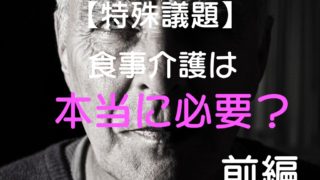

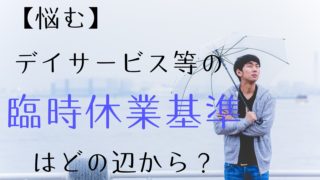

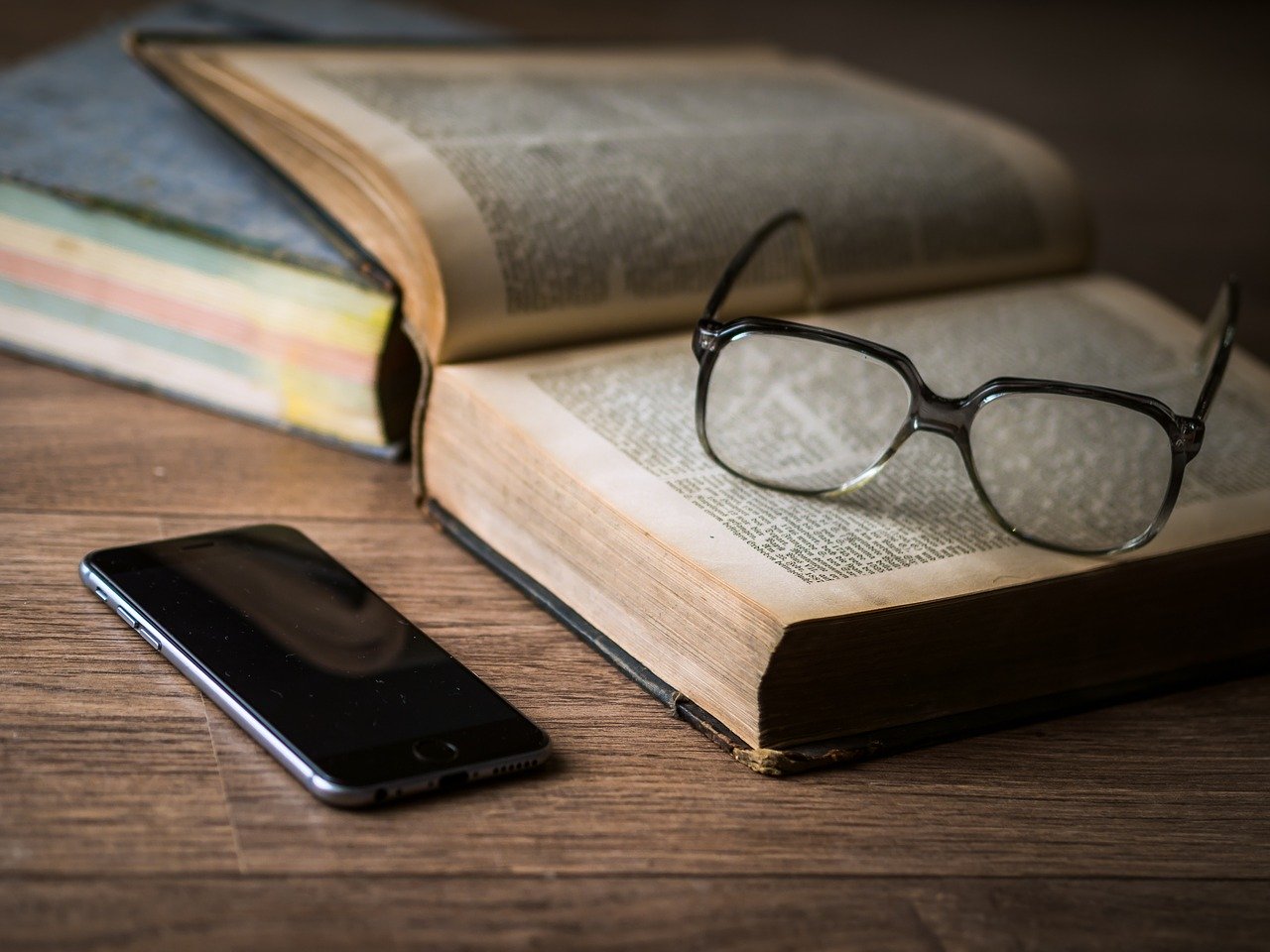


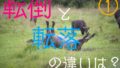

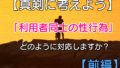


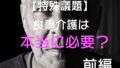


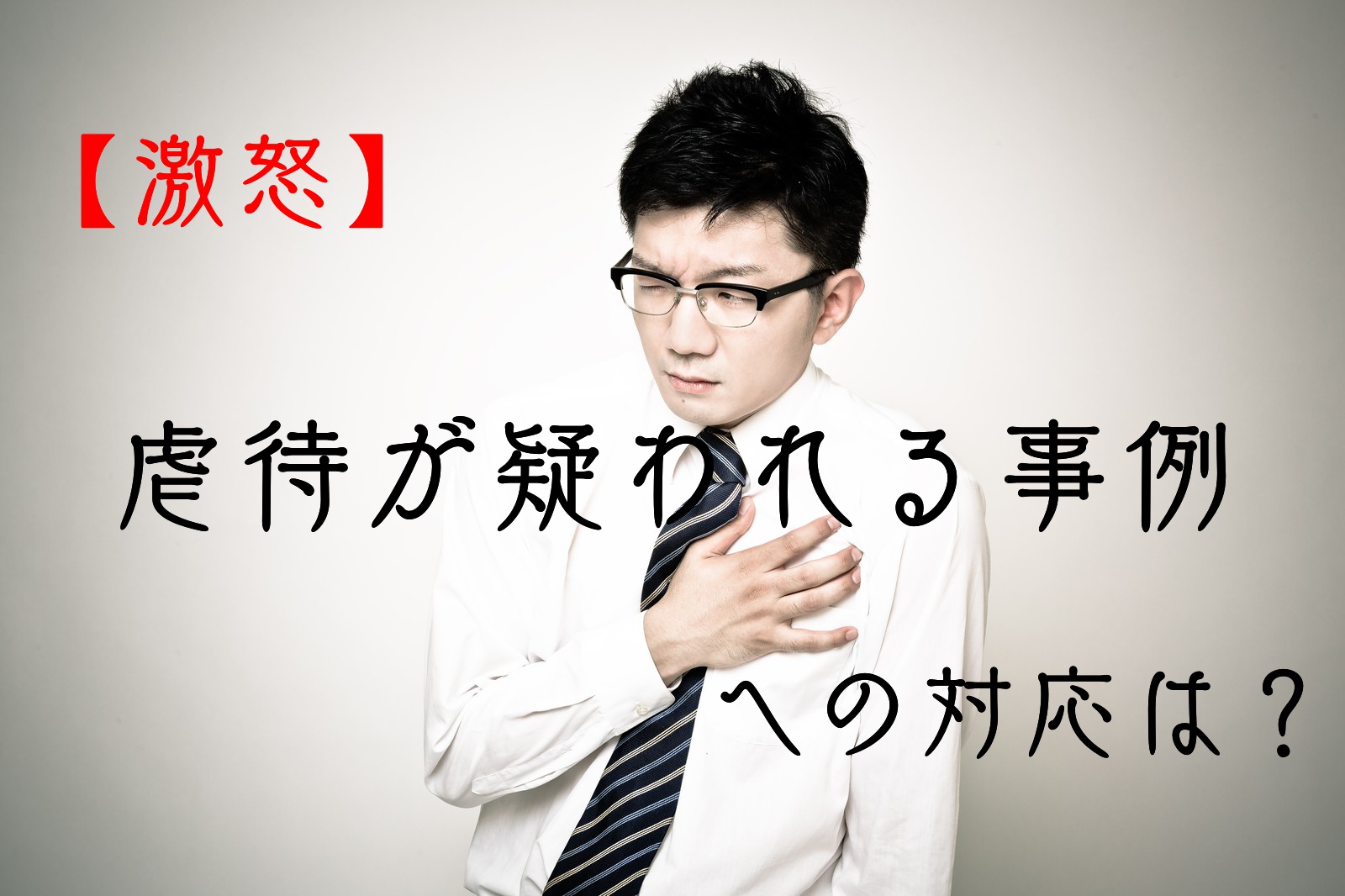
コメントはこちらから