
介護に外国語や、
手話は必要だと思いますか?
類似記事はこちら


必要だと思っています。
それは、病院勤務だとすれば、外来に先ず行かれて、
病棟に来られる事になります。
私の場合、急性期病棟で、外来の次に運ばれて来る患者が、
中国の方も多く来られてました。
多少の片言の日本語も話されてましたそして手話に関しても、
病院で毎朝朝礼で、
①おはようございます。
②いらっしゃいませ
③少々お待ち下さい
④ありがとうございます
⑤お大事にされて下さい。
この5つを、職場の教養を読みしていました。

今や飲食店等では外国人への配慮として
グローバルなメニュー表記などをされていますが、
何故公的な制度を用いた医療、介護、福祉に
わざわざ外国人への配慮が必要なのでしょうか?

人種差別は、あってはならない事だと思っています。
日本でもそれは、同じで、障がいがあるから、
ないからではありませんからね。
認知症に対しても同じ事です。

非言語コミュニケーション苦手な人が多すぎる。
外国語わからなくても、コミュニケーションする気持ちがアルかどうか?

確かに外国人を含めて
外部へのコミュニケーションに積極的になれるかは、
コミュニケーションの前提になるかと思います。
この議題はその前提は当然として、
次の段階において必要か否かになります。
私個人としてはあくまで必要かどうかは
必要ないと思っています。

お?意外です。
必要ないと思っているのですね?興味深い
手話も年齢差や生まれ、地域によって差がありすぎて
通じないから手話を学んだり外国語を学ぶ必要はないかも
その目の前に居る人が何を伝えようとしているのか?
感じる力が大事かな
看護職はこたえがあるからですね~?
対処法は決まっています。
こういう症例にはこの対処法という指標が
先に存在しています。
それを知らずにそもそも看護は務まりません。
診断して判断するのは看護職と医者ですね~。
その場合学ぶべき言語は一つであるべきですね~です。
アメリカ人でも日本人でも聴覚障害者でも
看護の世界では皆同じですね?
それってすごく根源的でスゴいことですね
人間だから血が流れればみんな赤い血を流すじゃないか?
ってこと体の作りに文化は影響しないですね?

私は現実的にまず体の作りなど
物理的な物に差がないことを前提にしています。
その上で文化など様々だと思いますが、
それでも一業界において
共通の思いや略語、方法はあると思っています。
あとは思いやり。これはまぁ理想論ですがね

外国語は必要だと思います。
実際に名古屋市の障害者基幹センターには、
外国人の相談件数が増えており、
受け入れ始めた施設もあるので今後は必要不可欠だと考えます。
手話は、平時はもちろん災害などで情報機器が使えない時に、
聴覚の方に、有効な伝達手段では無いでしょうか?

我々の業界では言語レベルの統一が情報伝達の基礎となります。
例えば、医療では卒業までに病名等の略語を習います。
略語はラテン語等です。現場でもラテン語等を使用しています。
あくまで対職員においてです。
対患者、対利用者においても、
結局は症状や状態に人種等は関係ないため、
あくまで世界共通言語を用いている以上、
新たに外国語等は必要ないのではと思います。

なるほど。仰っている意味はよく理解できます。
ただし、海外に視察に行った身としては、
職員にはこちらの文化や言語を理解する様にお話しするが、
利用者さん支援においては、あくまでも相手が主体、
相手の言語が主体かと考えます。
なので、例えば利用者さんがフインランド語を母国語とする場合、
こちらもフインランド語を取得し、フインランドの文化や価値観を
持って接するべきだと考えます。
自分が、海外に視察して痛感したのは他国に置いて、
自国の言語という物が、いかに無力になってしまうかというのを
痛感しています。
移民の方は母国語を遣う事が出来ず、
相手国の言語を学んで生活する事となります。
生活をする上で、母国語が使えないのは苦しみであり
孤独感だと考えます。
言葉は相手にとってアインデイティーであり、
価値観で有り、文化であると考えています。
もし、他国の利用者さんが来られた時、
例えば英語は世界共通語だからと英語で話しをして、
ある程度はご本人さんは話せますが、真なるニーズ、
自国の文化や価値観に根付いた要望を伝えきるのは
非常に困難であると考えます。
介護ではなく、障害者福祉の世界の概念かもしれませんが、
外国の方へかける言葉は、支援者側の判断ではなく、
本人の伝わり易く、より馴染んだ言語によるものと考えます。
利用者さんの代弁者であるならば、
利用者さんの母国語をしっかりと学び、
理解しなければより良いケアは難しいと考えます

郷に入りては郷に従えということですね。
あくまでもあちらサイドで話を合わすとなれば、
外国人への理解が前提になると思いますが、
ケア等に不十分が生じるかと思いますが、
そこにはどんな言語等を用いて対応されますか?

??
ケアをする上で、相手の言語に合わせなければ、
不十分なケアになってしまうとお伝えしたつもりですが??

すみません、わたしが言いたいのは
その不十分さを言葉だけで埋めることは出来ますか?
という趣旨でした。

そうですね。
外国人の方と接する上で難しいのは、
日本独自の文化や価値観や習慣が、
相手国には無い事が多いという事です。
例えば、フインランドでは入浴という習慣が無く、
入浴では無く、サウナ文化が根付いています。
何故サウナかというと、フインランドは北極圏に近いため
真冬はマイナス20度まで低下する事もあり、
汗をかく事が殆ど無いため、サウナに入って発汗して
心地よくなるという意味合いが有ります。
そのため、フインランド人にとって
「お風呂」は「サウナ」なんですね。
で、フインランドの方に「お風呂」と伝えると
「あ、サウナに入れるんだ」となってしまう訳なんです。

お風呂とサウナ、面白い。
サウナあるんですね。

真冬にサウナ入ってから、
プールで身体を冷やすって荒行か
何かがあるくらいなんで、サウナ文化ですね。
なので、相手の文化を理解しておかないと
全然同じ言葉だけど、別の意味に捉えられてしまうんですよ。
これが、お風呂位だったら、まだ笑い話で済むんですが、
宗教や少数民族等が絡んでくると、相手の尊厳や
アイデンティティーを傷つける事にも繋がりかねなく…
下手すれば人権問題にも関わる事もありうるので。
だから、相手国の言葉を覚えるだけではなく、
その言葉の意味合いが、相手の文化にとって
何を意味するのか正しく理解しておかないといけないかと考えます。
また、ジェスチャー等も日本ではOKな事が
外国の方には侮辱と捉えられる事もあるので、
外国の方の文化や価値観は支援者として、
理解しておく必要性があると考えます。

海外の話には恐れ入りました!
まだまだ後半へ続きます!!
後編はこちら
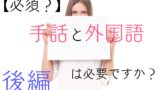

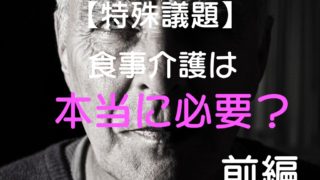



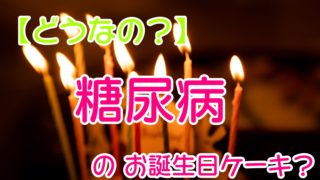
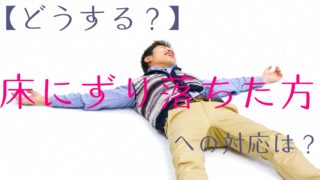
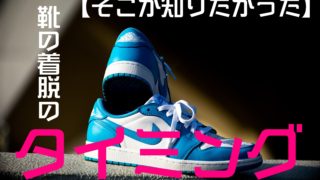
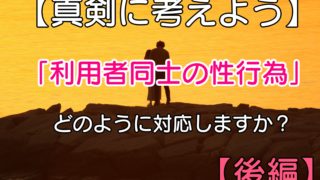
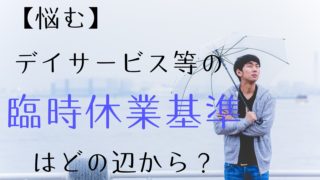


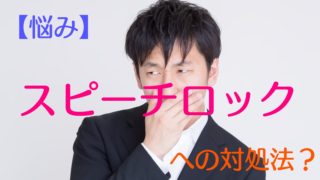
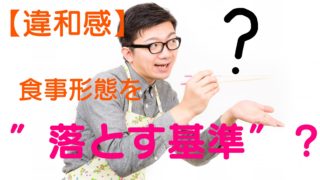
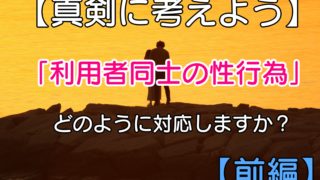

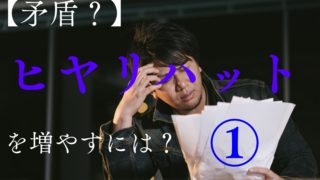
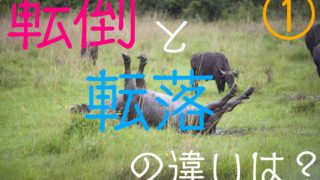
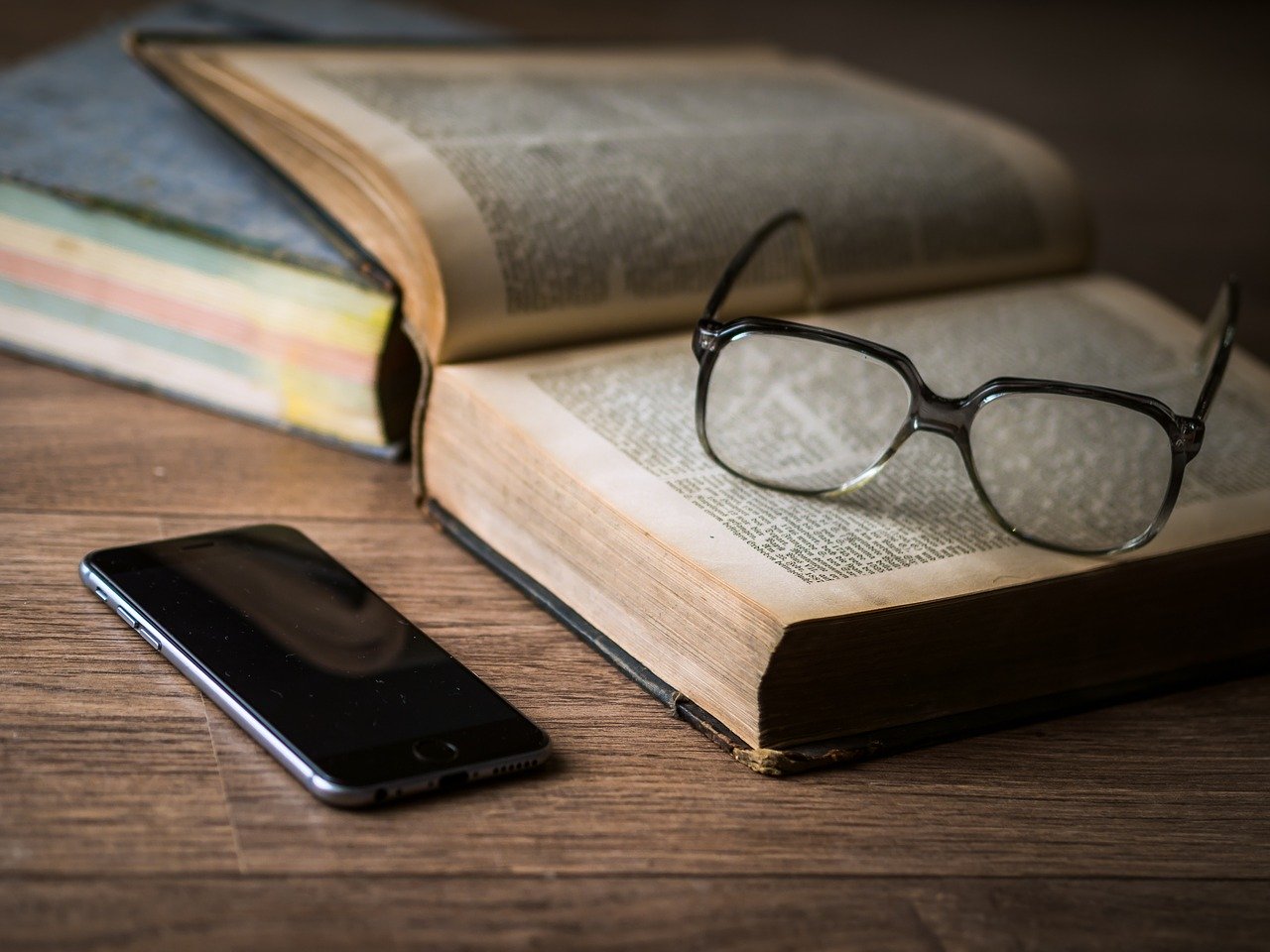


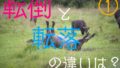

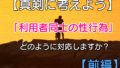


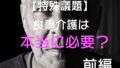


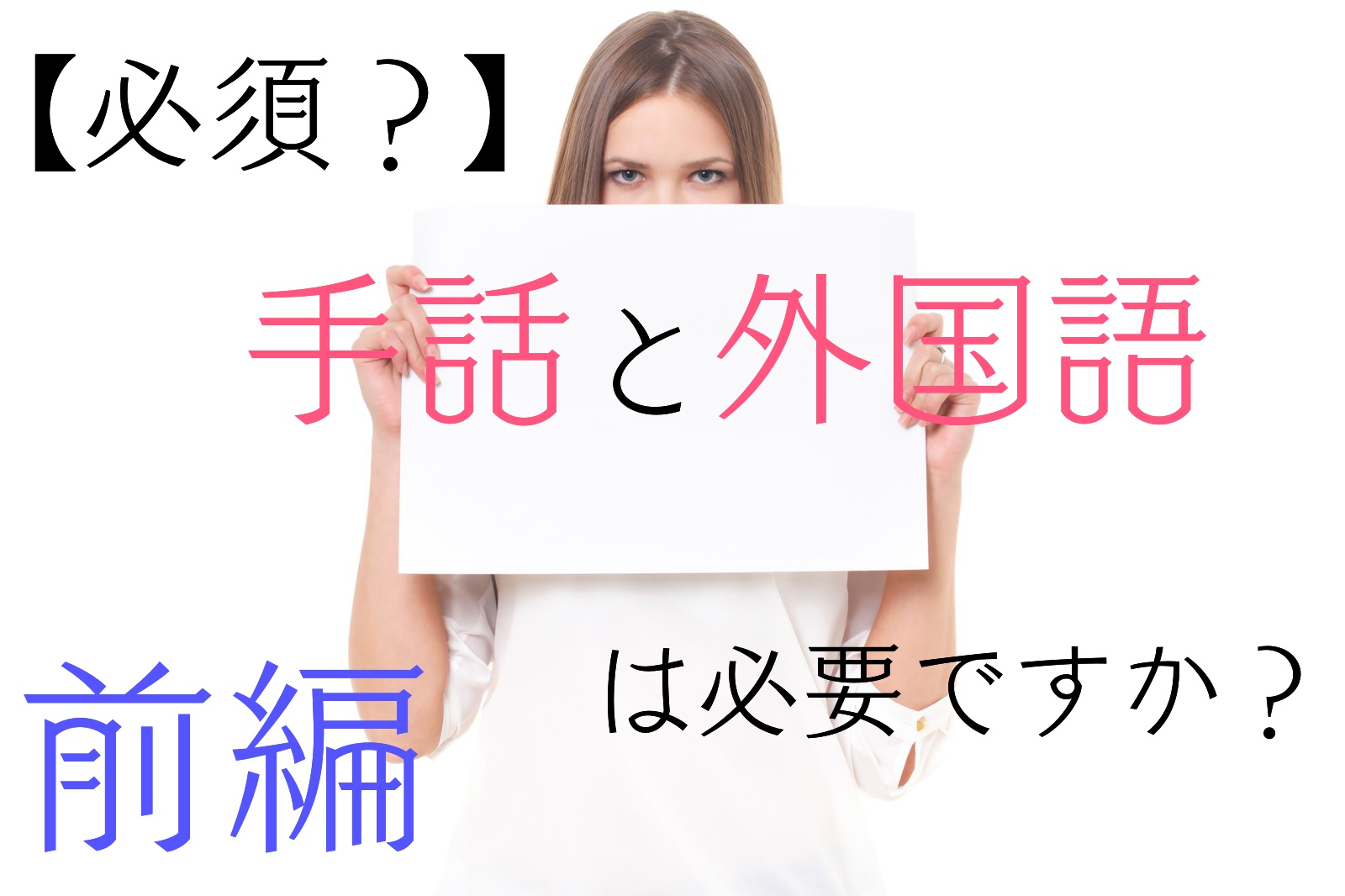
コメントはこちらから
[…] 【必須?】手話と外国語は必要ですか?前編我々の業界にも、外国人スタッフや障害雇用が盛んになってきましたね。 言語での悩みもあるのではないでしょうか? この議題で切り込み […]
[…] 【必須?】手話と外国語は必要ですか?前編我々の業界にも、外国人スタッフや障害雇用が盛んになってきましたね。 言語での悩みもあるのではないでしょうか? この議題で切り込み […]